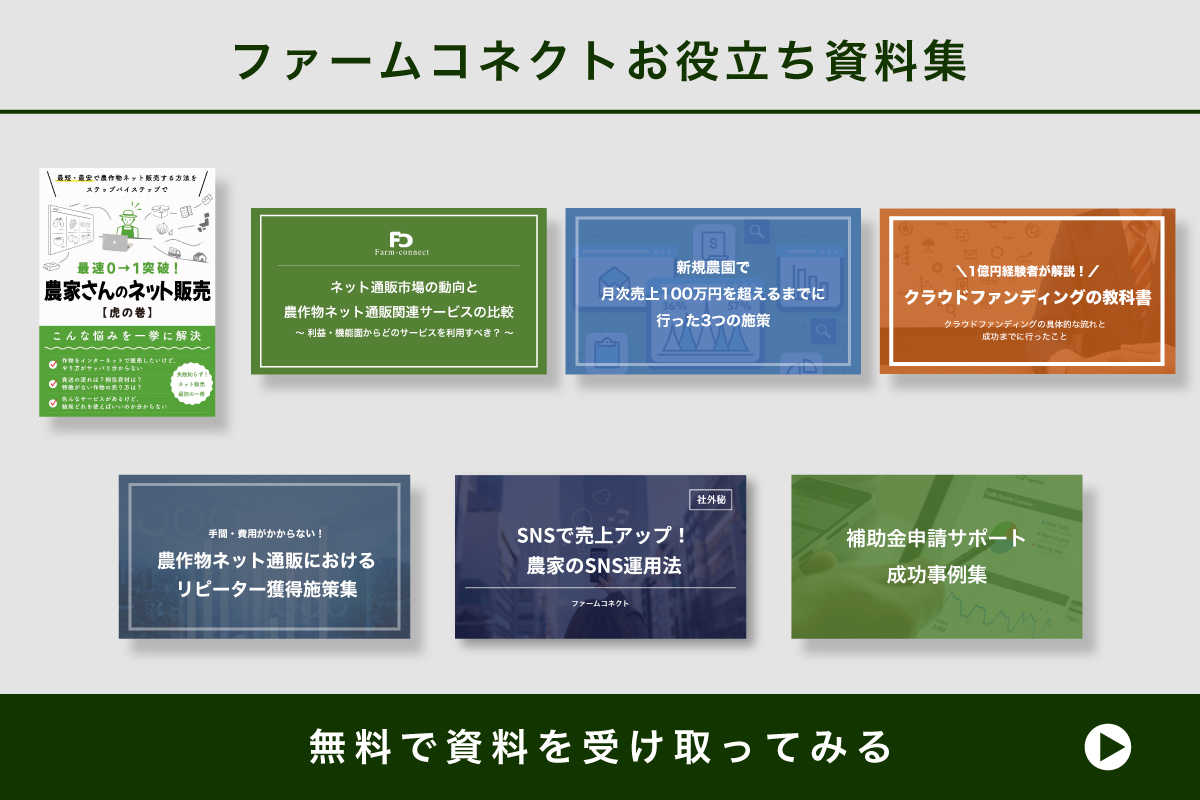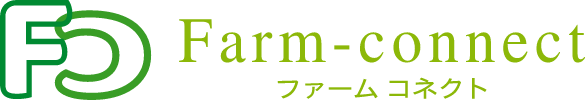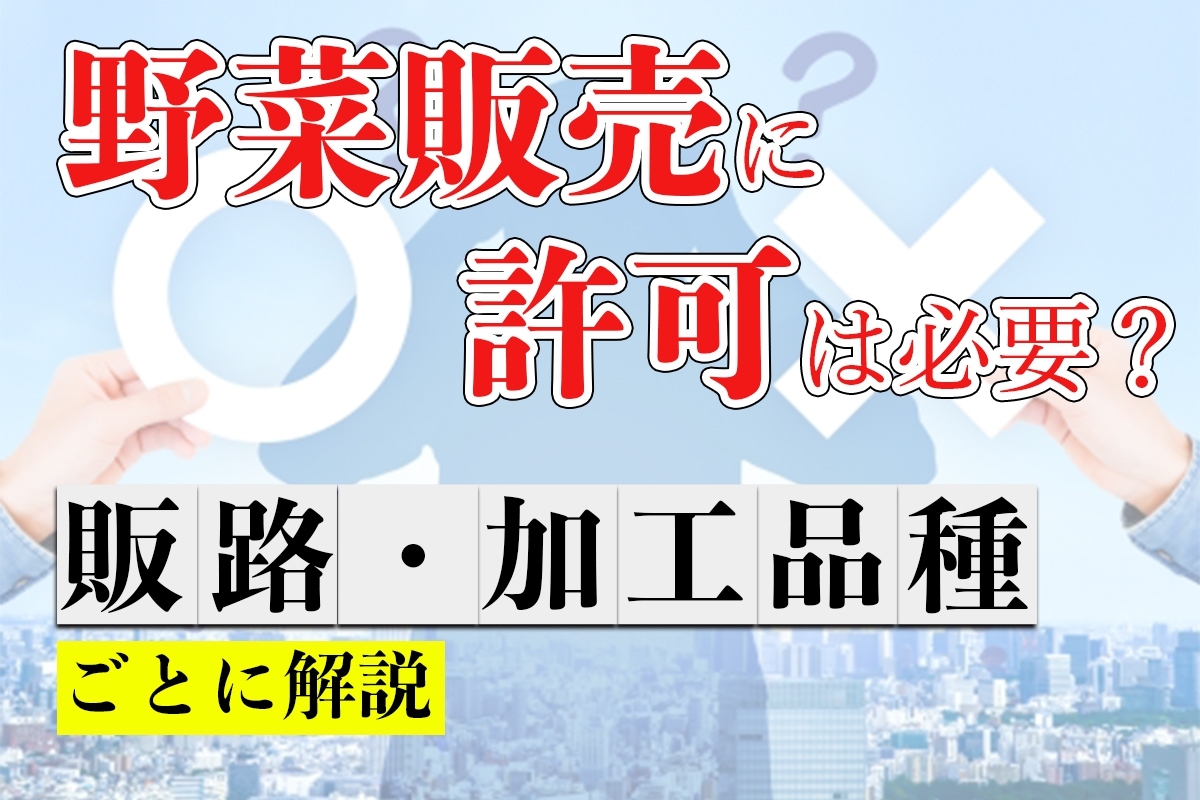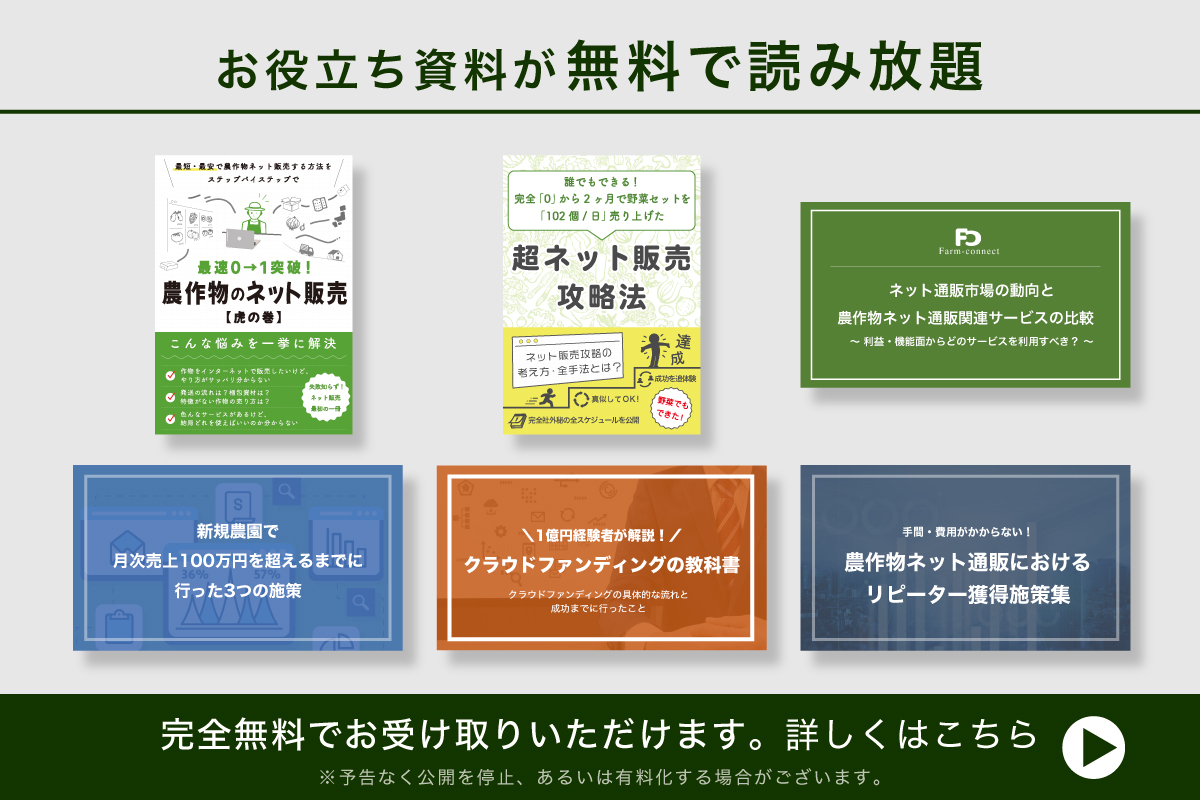新しい販路を活用して野菜や果物を販売したり、新しく加工食品を販売したいんだけど、許可が必要なのか気になる。
販路や加工品の種類ごとに許可の有無をまとめくれている記事はないかなあ。
こんな方に向けた記事です。
- 野菜販売の許可【販路別】
- 野菜販売の許可【加工品種別】
- 家庭菜園で育てた野菜を売るのに許可は必要か?
- 【番外編】野菜販売に関する法律
この記事は、直販支援を中心とする農業経営支援企業のファームコネクトが監修しています。ネット販売支援、ホームページ制作、デザイン制作、補助金申請サポートなど、農業経営にまつわる様々な領域を支援しております。
野菜で月次売上200万円、とうもろこしで日次売上100万円超えなど、多数の販売実績があり、行政とも提携している組織です。
今回は、野菜販売の許可について網羅的にお伝えしていきます。
野菜販売の許可【販路別】
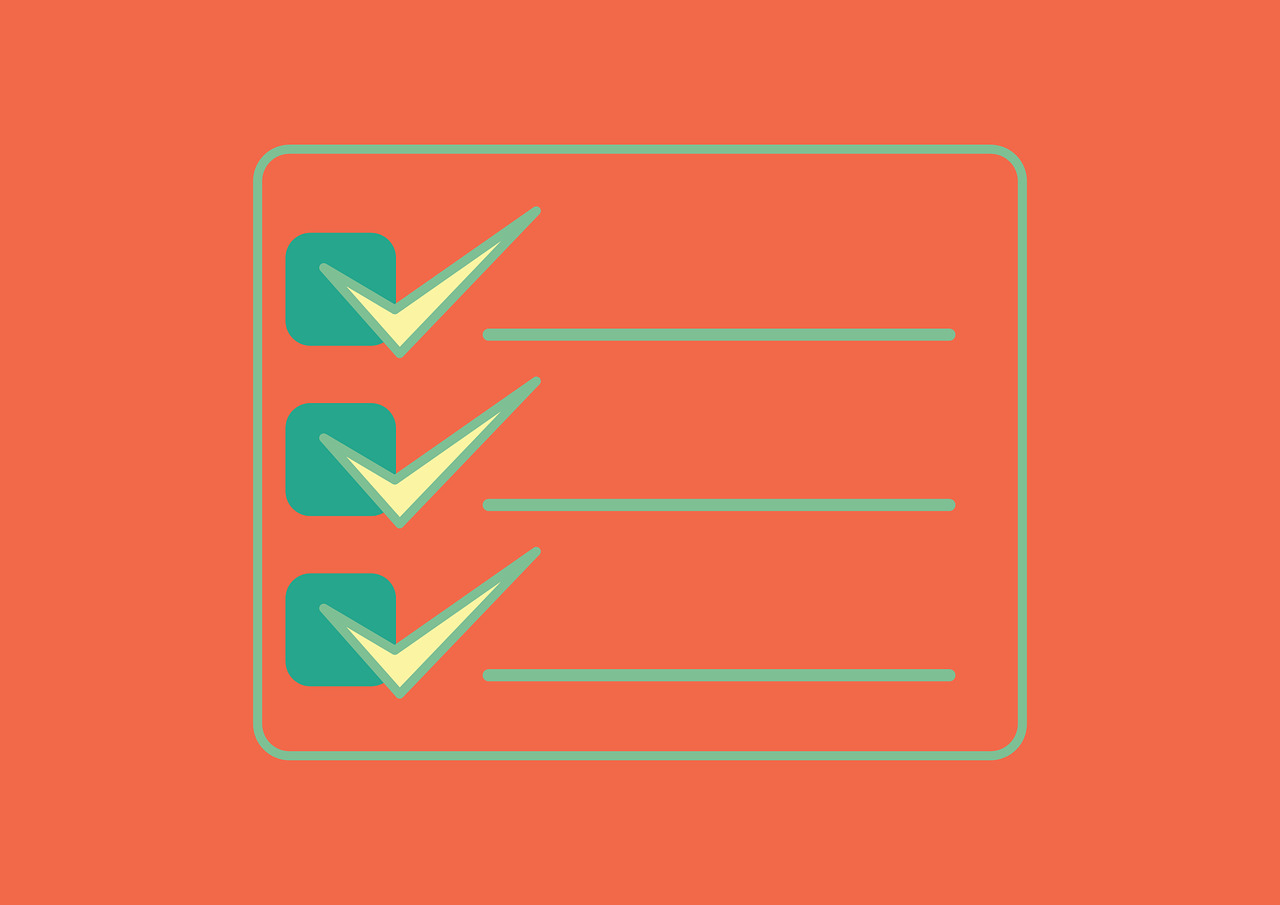
最初に、野菜販売の許可について、販路ごとに解説していきます。
本記事で紹介する販路は、ネット販売・無人販売・移動販売の3つです。
(他に解説してほしい販路があればコメント欄にて教えてください!)
野菜販売の許可【ネット販売】
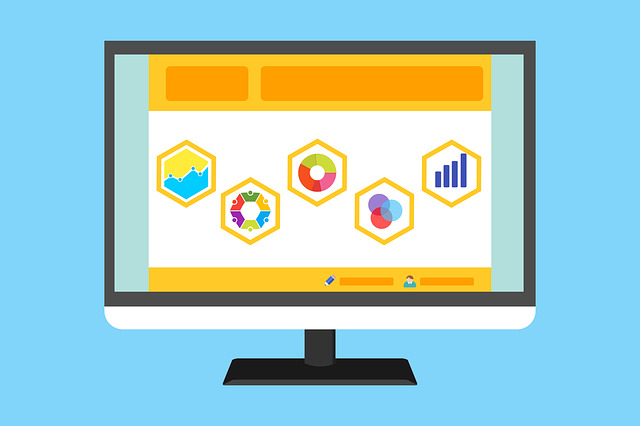
野菜のネット販売(通信販売)をおこなう際の許可についてお伝えします。
結論から述べると、野菜や果物のネット販売をするのに許可は不要です。
ただし、一つ注意点が。
それが特定商取引法の存在です。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
出典:特定商取引法ガイド
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
上記は消費者庁が運営するサイトの文言です。
ネット販売は特定商取引法の対象販路であることが分かります。
では、法律を守るために、具体的に何をすべきなのか。
最も重要なのが、通信販売サイトに「事業者の氏名・住所・電話番号」を記載することです。
この他に「販売価格の明示・商品の引渡時期の明示」などがありますが、これらは大半の事業者が特に意識せずとも載せていることでしょう。
その他の記載事項については、消費者庁のページをご覧ください。
野菜販売の許可【無人販売】

次に、野菜や果物の無人販売をおこなう際の許可について。
結論から述べると許可は不要です。どなたでも販売を開始することができます。
無人販売についても、「野菜の無人販売を始める方法と許可の有無まとめ」で詳しく述べているのでよかったらどうぞ。

野菜販売の許可【移動販売】
野菜や果物を移動販売するのに許可は必要なのか?について。
結論から述べると、販売自体に許可は不要です。
ただし、販売する場所については許可が必要となってきます。
公道であれば市区町村の役所で道路使用許可を取る必要がありますし、イベントスペースなどであればそこを運営している所に了解を得る必要があります。場所代が必要になるケースも少なくないので、事前に調査をして、出店できる場所を作っておくことは非常に重要です。
カスタム軽トラで野菜やパンを売りたい!移動食品販売にはどんな許可が必要?
道の駅やスーパー等の敷地内でも許可が必要ですよね。
移動販売については「野菜移動販売の開業に必要なもの・成功法を解説!」で詳しく解説しています。
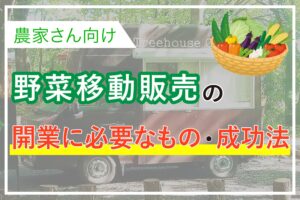
野菜販売の許可【加工品種別】

加工品の種類ごとに、販売許可の有無をお伝えしていきます。
本記事で紹介する加工品種は、乾燥野菜・漬物・ジャムの3つです。(他に解説してほしい販路があればコメント欄にて教えてください)
※自治体ごとに基準が異なるものもございます。加工販売を開始する前に、必ず各地の保健所に確認をお願いします。ファームコネクトは一切の責任を負いかねます。
野菜加工品の販売許可【漬物】

もともと、自治体によっては許可が不要だった漬物製造ですが、令和3年の食品衛生法改正により、全国的に「漬物製造業許可」と呼ばれる許認可が必須となりました。
許認可を取得するには、厚労省が定めた基準をクリアした「施設を準備」し、審査を受ける必要があります。(=自宅での製造は不可)
ただし、令和6年までは「移行期間」として、これまでの漬物作りが許容されています。
野菜加工品の販売許可【乾燥野菜】

野菜を乾燥させただけなので、加工品として扱うか迷いますよね。
結論から述べると、作物により異なります。
丸干しや乾燥キノコの場合:許可は不要(食品表示法に基づくラベル貼付は必要)。
干し柿、干し芋、切り干し大根の場合:営業届および食品表示法に基づくラベル貼付が必要。
野菜・果物加工品の販売許可【ジャム】
近ごろは手作りジャムを作る人も多いですよね。
果樹農家さんにもジャムを手作りして販売する人が多いのではないでしょうか?
もともと、ジャムの販売許可は都道府県によって異なりました。
しかし、漬物同様、令和3年の食品衛生法改正により、「密封包装食品製造業許可」と呼ばれる許可が必須となっているので注意が必要です。
また、ジャムは食品表示法によりラベル貼付が義務付けられています。
【番外編】家庭菜園で育てた野菜を販売するのに許可は必要?

最後に、家庭菜園で育てた野菜を販売するのに許可は必要かどうかについて。
結論から述べると、許可は不要です。いつでも売り出すことができます。
無人販売で販売してみてもいいですし、メルカリなどのフリマアプリを活用してもいいでしょう。
ただし、加工品の場合は許可が必要なのでご注意ください。
【番外編】野菜販売に関する法律
景品表示法、薬事法、農林水産省ガイドラインなどに注意が必要です。
景品表示法
景品表示法という、不当な広告を規制する法律があります。
かの有名なステルスマーケティングも、この景品表示法によって規制されています。
なお、ステルスマーケティングとは、「広告であることを隠して広告宣伝すること」です。
例えば消費者に、「こういった口コミで商品を紹介してください」と口コミの内容を指定してクチコミを投稿させることは違反となります。
また、インフルエンサーに商品を紹介してもらう際には「PR表記」が必須です。
景品表示法については、一度全体に目を通してから野菜販売することをお勧めします。
→景品表示法
薬事法
もしも農作物をサプリメントにして販売する場合、薬事法に遵守する必要があります。
例えば、「水と一緒にお飲みください」など、サプリメントの飲み方を指定することは、医薬品と間違われる可能性があることから薬事法で禁止されています。
薬事法は非常に厳しい法律で、また定期的に改正がありますので、随時ウォッチしておく必要があります。
とはいえ難解な法律となりますので、もしもサプリメントを販売する際は弁護士にリーガルチェックを依頼することをお勧めします。
その他の注意点
農業においては「減農薬」「無農薬」「自然栽培」といったキーワードは使用しないよう農林水産省のガイドラインで定められています。
「有機栽培」というキーワードも、有機JAS認証を取得している必要があるので注意しましょう。
※有機質肥料を使用しているが、有機JASを取得していない場合は、控えめに「有機質肥料を使用している」と記載している程度であれば問題ないようです。
また、農薬を使用していない場合は、「無農薬」ではなく「栽培期間中、農薬不使用」という表現が適切です。
野菜の販売に許可は必要?まとめ

以上、野菜販売に必要な許可についてでした。
全体を通して、自治体によって異なるケースが多いので注意が必要です。
条例をしっかり守って、安心して野菜を販売していきましょう!
なお、野菜のネット販売に興味がある方に向けて、以下の記事でネット販売の始め方を徹底解説しています。よければご覧ください。