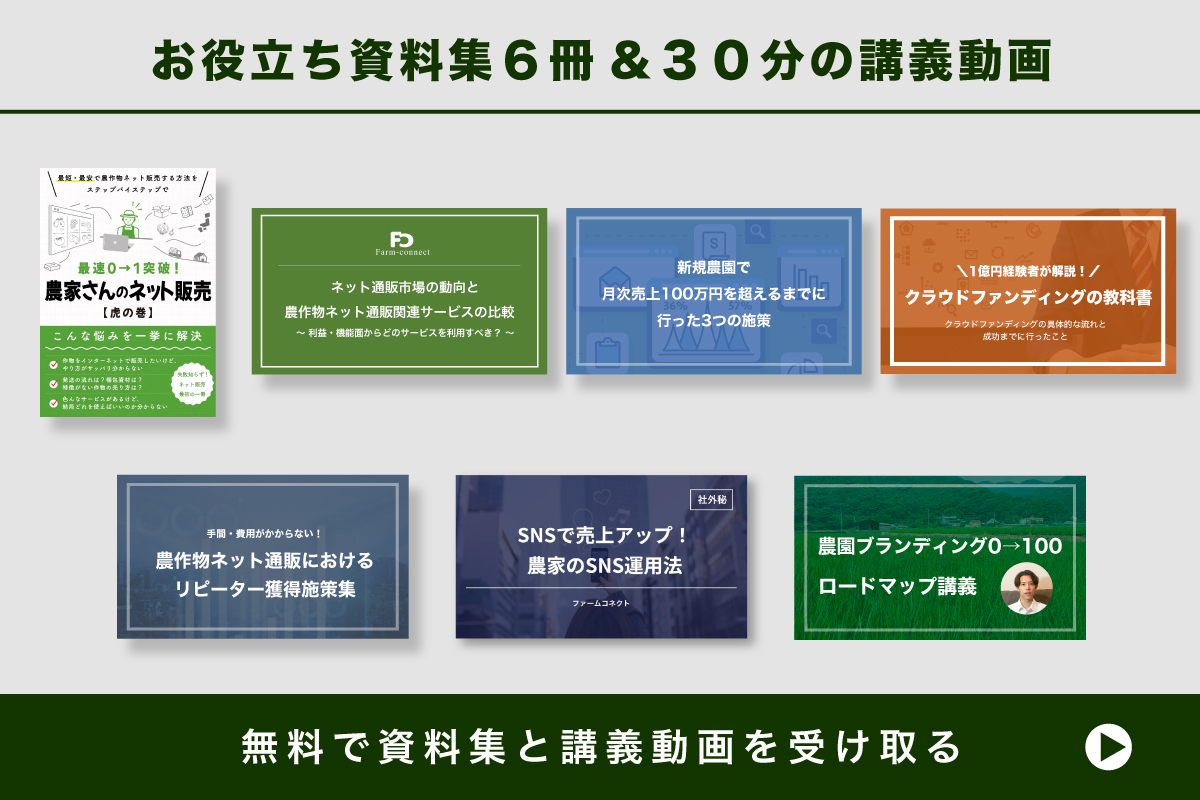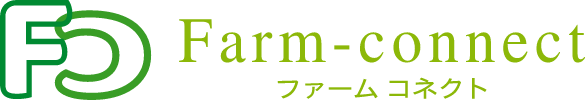農業で法人化するか悩んでる。
法人の設立費用はどのぐらいかかるのかな?
こんな方に向けた記事です。
この記事は、直販支援を中心とする農業経営支援企業のファームコネクトが監修しています。ネット販売支援、ホームページ制作、デザイン制作など、農業経営にまつわる様々な領域を支援しております。
野菜で月次売上200万円、とうもろこしで日次売上100万円超えなど、多数の販売実績があり、行政とも提携している組織です。
そもそも農業法人とは?
「農業法人」とは、稲作等の土地利用型農業、施設型園芸、畜産業など、多様な農業経営を行う法人の総称です。
その組織形態は主に、会社法に準拠した株式会社・合名会社といった「会社法人」と、農業協同組合法を法的根拠とする「農事組合法人」の二つに大別されます。
農業法人と株式会社の違い
農業法人とは、農業経営を行う法人の総称であり、多様な法人形態を含んでいます。
その中で、会社法に基づく株式会社は、農業法人の6つの形態のうちの1つに位置づけられます。
同様に、会社法が規定する「合同会社」「合資会社」「合名会社」についても、それぞれが農業法人としての経営形態の選択肢となります。
各法人形態には固有の特徴と法的要件が存在するため、事業目的や経営方針に応じた適切な形態選択が重要です。
【注意】農地を所有するには農地所有適格法人になる必要がある
農業法人が農地を取得・所有するためには、農地法が規定する要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たした法人を「農地所有適格法人」といい、農地の所有権取得が認められます。
具体的な要件は、農林水産省公式HPで確認できます。
農業法人を設立するメリット
農業法人を設立するにあたり、以下の3つの側面でさまざまなメリットが発生します。
- 経営面
- 地域農業
- 制度面
経済面でのメリット
経済面でのメリットその①:経営管理能力の向上
法人化することでその経営責任を改めて自覚し、経営者としての意識が強まるケースが多いです。
また、家計と経営を完全に分離する必要があるため、個人農園に多いドンブリ勘定からの脱却を目指すことができます。
経済面でのメリットその②:対外的な信用の向上
法人化すると、財務諸表の作成が義務付けられます。
財務状況が公的に記録されていることで、金融機関や取引先からの信用が増し、融資や取引がスムーズに進むことがあります。
経済面でのメリットその③:経営発展の可能性
個人農園に比べて、農業法人では幅広い人材の確保が可能となります。
さまざまな能力を持った従業員を採用することで経営が多角化し、事業展開の可能性が広がります。
経済面でのメリットその④:福利厚生の充実
社会保険や労働保険の適用、就業規則の整備や就業条件の明確化など、農業従事者の福利厚生の拡充を目指すことができます。
経済面でのメリットその⑤:柔軟な経営継承
個人経営の農園では、基本的に、その家族があとを継ぐケースが多くなります。
しかし農業法人では、構成員や従業員の中から後継者を決めることも可能なため、より優秀な人材に経営を継承することができます。
地域農業としてのメリット
地域農業としてのメリット①:新規就農者の採用
新規就農を目指す人の枷となるのが、一人前となるまでの初期負担です。
農業法人で新規就農者を採用し、働きながら経営や農業技術について学ぶ機会を与えることで、地域全体の農業を活性化するきっかけとなります。
制度面でのメリット
制度面でのメリット①:税制
役員報酬は法人税において損金算入が可能で、所得税において役員が受け取った報酬は、給与所得控除の対象です。
この制度を活用し、役員報酬を給与所得とすることで、大幅な節税になります。
また、欠損金がある場合、10年間繰り越し控除を受けることも可能です。
青色申告をしている個人事業主の控除期間が3年間であることと比べて、大きな違いがあります。
制度面でのメリット②:融資限度額の拡大
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額は、個人と法人で下記の通りです。
- 個人:3億円(複数部門経営は6億円)
- 法人:10億円(民間金融機関との協調融資の状況に応じ30億円)
農業法人を設立するデメリット
農業法人の設立にはさまざまなメリットがある一方、デメリットも存在します。
- 社会保険料の負担が増える
- 設立・維持のコストが発生する
- 農地所有適格法人の要件を満たすのが困難
それぞれについて、詳しく解説していきます。
農業法人のデメリットその①:社会保険料の負担が増える
経営を法人化すると、その分コストがかかります。
例えば、条件を満たした従業員は社会保険に加入させる必要がありますし、これまで国民健康保険と国民年金に加入していた経営者も、新たに社会保険に加入しなければなりません。
福利厚生の充実につながる一方、会社の保険料負担は大きくなります。
農業法人のデメリットその②:設立・維持のコストが発生する
法人は、設立と維持にコストがかかります。
設立時には、定款認証の手数料や登録免許税など、株式会社の場合で約20万円の支払いが必要です。
また、万が一利益がない場合でも、最低限の法人住民税を支払う義務があります。
農業法人のデメリットその③:農地所有適格法人の要件を満たすのが困難
先ほど解説した通り、農業法人が農地を取得・所有するためには、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
要件は多岐にわたりますが、どれも法人としてしっかりと農業に向き合うことが求められており、そのすべてを満たすのは簡単ではありません。
農業で法人化するタイミングの目安
農業で法人化するタイミングの目安として、所得が500~600万円を超えたころがよいとされています。
法人化することによる税制上のメリットが大きくなり、法人税の方が有利になる場合が多いためです。
また、従業員の拡充や経営規模の拡大を目指すタイミングも、ひとつの基準となります。
農業法人のメリット・デメリットを考慮し、決断することが重要です。
農業法人設立の流れ
農業の法人化には複雑な手続きが必要です。
以下に主要な手続きを説明しますので、順を追って進めてみてください。
まずは、設立する会社の形態を決めましょう。
一般的に農業法人は、株式会社または合同会社として設立する場合が多いです。
それぞれメリットとデメリットがあるため、事業規模や運営方針に応じて選択します。
- 株式会社:株主が出資し、取締役会を設置することで経営の透明性を確保できる
- 合同会社:出資者全員が経営に参加できる柔軟な運営
次に、定款を作成します。
定款とは、会社の基本ルールや事業内容を定める重要な文書で、下記のような会社の基本情報を記載します。
- 会社名
- 所在地
- 目的
- 株式の内容
- 役員の任期
- 取締役の選任方法
※記載内容の一部です
株式会社の場合、定款は創業者である発起人が作成し公証人の認証が必要です。
一方、合同会社の場合は認証が不要です。
会社名義の銀行口座を開設します。
設立後の資本金の払い込みや経営資金の管理に使用しますので、必ず新しく解説しましょう。
法人の銀行口座開設には、下記のようなさまざまな書類の提出が必要です。
- 定款
- 印鑑証明書
- 設立趣意書
※必要書類の一部です
また、銀行によっては厳しい審査が実施されることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
資本金の払い込みを終えたら、法務局に会社開設の登記申請を行います。
登記申請に必要な書類は下記の通りです。
- 定款
- 振込証明書
- 取締役会議事録
- 設立登記申請書
※必要書類の一部です
登記が完了すると、正式に法人としての活動がスタートします。
手続きには専門的な知識が必要なため、司法書士や行政書士などの専門家に依頼すると安心です。
法人設立後は、個人事業主の廃業手続きを行います。
廃業手続きには、税務署、市区町村役場、年金事務所などへ赴き、廃業届の提出、所得税の青色申告承認申請書の取り下げ、事業用資産の売却・譲渡に関する手続きなどが必要です。
ここまで完了したら、最後に、下記の手続きを済ませていきます。
- 税務署へ法人設立届出書を提出
- 社会保険への加入手続き
- 法人名義の契約書類の更新
※必要手続きの一部です
設立後にも必要な手続きは多くあるので、漏れの内容に注意しましょう。
農業で法人を設立する際にかかる費用
農業法人の設立にかかる費用は、以下の通りです。
| 公証役場の定款認証手数料 | 30,000~50,000円 |
| 収入印紙代 | 40,000円 |
| 謄本交付料 | 2,000円程度 |
| 登記をする際の登録免許税 | 150,000円~ |
| 専門家への報酬 ※手続きを依頼する場合 | 100,000~200,000円 |
| 合計 | 322,000円~ |
必要経費ではあるものの、資金面のリスクはなるべく抑えたいもの。
事業用資金の調達方法はさまざまですが、国や地方自治体による補助金・助成金の活用も選択肢になります。
農業法人設立費用まとめ
以上、農業法人設立のメリット・デメリット、手続きとその費用でした。
適切なタイミングでの法人化は、その後の経営を大きく伸ばすきっかけとなります。
補助金を活用するなどリスクを減らしながら、法人設立に挑んでいただければと思います!
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。